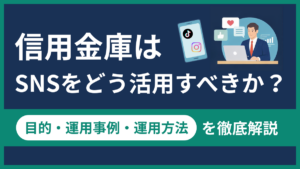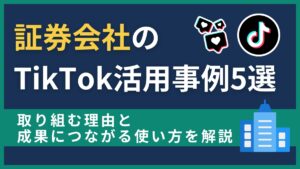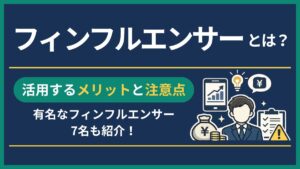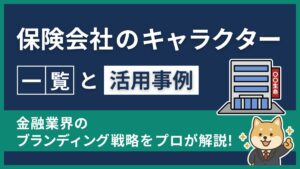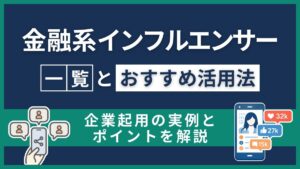銀行のコンテンツマーケティングとは?成功事例7選と戦略・運用ポイントをプロが解説
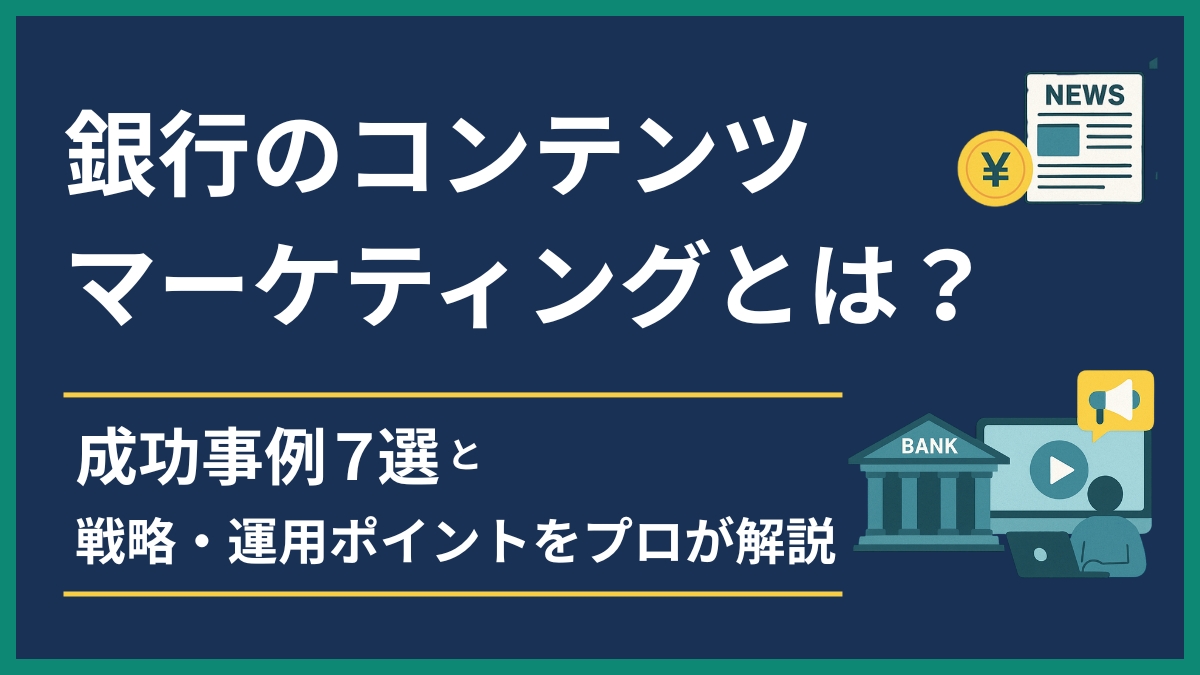
銀行業界でも近年、オウンドメディアやSNS、動画配信、オンラインセミナーなどを活用したコンテンツマーケティングの重要性が急速に高まっています。その背景には、店舗来店数の減少や非対面チャネルの拡大に伴い、顧客との接点を多様化させる必要が生じていること、さらにブランド価値の向上や若年層への認知拡大といった課題があります。
しかし現場では、「どんなテーマを扱えば読まれるのか」「始めたはいいが成果が数字で見えない」といった悩みを抱える広報・企画・営業推進部門の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、金融機関に特化したコンテンツ支援を行う筆者(ファイマケ代表・苛原寛)が、銀行のコンテンツマーケティング成功事例7選を厳選紹介。加えて、取り組みが増えている背景や、成果を最大化するための設計ポイント、KPI設定のヒントまで実践的に解説します。
これから導入を検討している銀行はもちろん、すでに施策を進めているが改善の余地を感じている担当者にとっても、現場で活かせる具体的な学びとなるポイントを紹介していきます。
- 銀行の広報・マーケティング・営業企画を担当し、新しい集客施策やブランド発信に悩んでいる方
- コンテンツマーケティングを始めたいが、どんなテーマや媒体から取り組めばいいか迷っている方
- 上司や経営陣に提案するための、説得力ある他行事例やKPIの参考データを探している方
- 他行の施策調査や競合分析を求められた広告代理店・制作会社の担当者
コンテンツマーケティングに取り組む銀行が増えている理由とは
銀行業界でも近年、従来の広告や店頭営業だけに頼らず、顧客の関心や課題に寄り添ったコンテンツを発信する取り組みが広がっています。金融商品の比較検討は情報収集が重要で、顧客がネット上で自ら調べる行動が一般化した今、銀行側も早い段階から信頼を得るための情報提供者としての役割が求められるようになりました。
ここでは、銀行がコンテンツマーケティングに取り組む背景を3つの視点から整理します。

顧客の情報収集能力が高まっているから
スマートフォンやSNSの普及により、金融商品の検討プロセスは大きく変化しました。かつては店頭やパンフレットで説明を受けてから比較する流れが主流でしたが、今では顧客自身が検索やSNSで情報を集め、比較検討してから銀行を訪れるケースが増えています。
銀行は、顧客が調べている段階から接点を持つ必要があり、検索ニーズに沿った記事や動画を提供することで、信頼できる情報源として認知されやすくなります。結果として、店舗来訪前から顧客との関係構築が可能となり、選ばれる確率を高めることができます。
商品やサービスの差別化が難しい時代だから
銀行が提供するサービスには、預金・ローン・投資信託など多くの共通点があります。だからこそ、お客さまに選ばれる銀行になるためには、「どこで口座を開きたいか」「どの銀行に相談したいか」といったお客さまの気持ちや期待に寄り添うことが大切です。
コンテンツマーケティングは、商品説明だけでなく、ライフイベント別の資産形成術や住宅購入の流れ、教育資金の準備方法など生活に密着した情報を提供することで差別化を実現します。
信頼性やエンゲージメントを向上させるため
金融機関は「難しい」「堅い」というイメージを持たれがちです。コンテンツマーケティングを通じて、専門用語をかみ砕いた説明や実際の体験談を交えた記事を発信することで、銀行に親近感を持ってもらえるようになります。
また、SNSやメディアで発信することで双方向のコミュニケーションが可能となり、顧客の疑問や声をリアルタイムで拾い上げることもできます。結果的に「信頼できるパートナー」としてのブランドイメージが確立し、顧客のロイヤリティや利用頻度の向上につながります。
 ファイマケ代表 苛原寛
ファイマケ代表 苛原寛銀行のメディア発信は信頼性を担保することが最も重要です。難解な表現を避け、ユーザーに寄り添ったトーンで説明することで初めて共感が生まれます。双方向のコミュニケーションを意識すれば、単なる情報提供ではなく選ばれる金融パートナーへと成長できます。
銀行のコンテンツマーケティングの手法5選
銀行のコンテンツマーケティングは単なる情報発信ではなく、顧客との信頼関係を築き、長期的な関係を維持するための仕組みです。特に金融業界は専門性が高く、生活者が正しい判断をするために必要な情報を分かりやすく提供することが重要です。ここでは、銀行がよく活用している代表的な手法を5つ紹介します。
オウンドメディアによる情報発信
オウンドメディアは、銀行が自社で運営するWebサイトやブログで、生活者に役立つ情報を継続的に発信する施策です。預金、投資、住宅ローンなどの商品解説だけでなく、家計管理術やライフイベント別の資産形成方法、最新の税制改正のポイントなど、顧客の関心に沿ったテーマを提供します。
SNS運用での情報発信
TwitterやInstagram、YouTubeなどSNSは、銀行と顧客の双方向コミュニケーションを実現する場です。たとえば、経済ニュースをかみ砕いて解説する投稿や、ストーリーズでのQ&A、ライブ配信による投資セミナーなどは、顧客の疑問解消に役立ちます。
特に若年層は店舗よりもオンラインでの接点を重視する傾向があるため、SNS活用はブランド認知の拡大と親近感の醸成に効果的です。投稿の反応を分析すれば、顧客が今どんな悩みを抱えているかを把握するヒントにもなります。



SNSは告知のみではなく、顧客の声を直接拾えるチャネルです。リアルタイム性を生かしてタイムリーに対応することで、銀行の誠実さや信頼性を伝えられます。とくに若年層との接点拡大には欠かせない取り組みといえるでしょう。
メールマガジン・プッシュ通知による接点強化
アプリやメールを活用して、顧客ごとにパーソナライズされた情報を届ける手法も有効です。たとえば、資産運用を始めたばかりのユーザーには基礎知識をまとめた記事を、住宅ローン検討中のユーザーには金利動向やシミュレーションの情報を案内するなど、状況に応じて出し分けることで、顧客満足度が高まります。
セミナー・ウェビナーの開催
店舗やオンラインでのセミナーは、銀行が持つ専門知識を直接提供できる貴重な機会です。最近ではウェビナー形式が主流になり、全国どこからでも参加可能。
投資信託やNISA、iDeCoの仕組み解説だけでなく、家計改善やライフプランニングをテーマにした講座も人気です。質問コーナーを設けることで参加者との対話が生まれ、銀行に対する信頼感が高まります。録画コンテンツを後日配信することで、参加できなかった層にも情報を届けられる点もメリットです。
自社アプリで継続的な関係を構築
SNS上で顧客の声や体験談を発信し、自社アプリへの導線を設けることで、より身近でリアルな共感を生み出すことができます。たとえば、教育資金を準備する30代夫婦や、退職後の資産運用を考えるシニア層など、実際の利用者ストーリーをSNSで紹介し、詳細はアプリ内で読める形にすれば、ユーザーは自然とアプリを訪れるきっかけを得られます。
SNSでは共感や発見を促し、アプリでは理解や行動へつなげる流れを意識することで、情報発信だけではなく、顧客との継続的な関係構築が可能になります。



金融サービスは、数字や制度の説明だけでは伝わりにくい部分が多いです。事例紹介を交えることで、顧客は自分にも挑戦できそうという感覚を持ちやすくなります。共感を通じてブランドの信頼感を強化するには、ストーリーテリングが非常に効果的です。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例【オウンドメディア編】
銀行がオウンドメディアやコンテンツ発信を強化する動きが加速しています。従来の金利や手数料の比較中心の情報提供から、お金にまつわる知識・ライフプランをテーマにしたコンテンツへとシフトしてきました。それにより、信頼獲得や顧客接点の拡大、中長期の囲い込みなどの成果を生んでいる事例が増えています。
ここでは、りそな銀行とauじぶん銀行の取り組みを紹介しながら、成功の要因を探っていきます。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例①りそな銀行


りそな銀行が運営する「暮らしが変わる お金の勉強」では、資産運用、ローン、キャッシュレス、老後資金、保険など、多岐にわたる「お金にまつわるテーマ」が体系的に整理され、読者が自分に必要な情報にたどりつきやすい構造になっています。サイトのナビゲーションには、「みんなが知りたい資産運用」「お得で便利なキャッシュレス」など、読者の関心を引きやすいカテゴリが並んでいます。
記事は専門性を保ちつつ日常的な言葉で噛み砕いて書かれており、iDeCo、確定拠出年金、節税対策といったやや難しいテーマも、見出し構成や事例紹介、Q&A形式などを活用して読みやすくしています。さらに、ユーザーのリピートや拡散を後押しするランキング機能・記事の保存機能・検索機能・シェア機能なども備えており、読者をサイト内で回遊させやすい設計となっています。
また、りそなグループでは動画教材コンテンツも併設しており、子どもから大人まで幅広い層に対して金融経済知識を伝える「動画で学ぼう!りそなの金融経済教育」などを提供しています。これにより、テキストでは伝わりにくい概念やビジュアル要素が必要なテーマを、視覚的にも理解できる形で展開しています。
運営面では、りそな銀行自身がWebサイト改善を通じて、顧客の行動データをもとに最適なコンテンツ表示や誘導を行うデジタルマーケティング戦略を実践しています。たとえば、CXプラットフォーム「KARTE」を導入し、ユーザーの行動履歴に応じたコンテンツ提示を行うことで、サイト訪問者を効率的に誘導。これによりアクセス数が3年間で1.7倍、費用対効果も単年で2.5倍に向上させたという改善実績も報告されています。
このように、「暮らしが変わる お金の勉強」は、読み手にとって有益な情報を軸に、UXや誘導設計、データ活用を組み合わせたメディア構成を実現しており、金融機関によるオウンドメディア運営の成功例といえます。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例②auじぶん銀行


近年、ネット銀行としてスマホ中心のサービス設計を強みとするauじぶん銀行は、「お金に関する知識を提供するメディア発信」も積極的に行っています。同社の公式サイトではコラムが設けられ、インフレ、投資用語、住宅ローン、家計管理などのテーマを扱う記事が豊富に公開されており、ユーザーにとって「知りたい情報を見つけやすい構造」になっています。「インフレとは何?」や「インカムゲイン・キャピタルゲインとは?」などの基礎的なテーマを、初心者にも理解しやすく解説する記事が人気となっており、専門家監修のコンテンツも多くあります。
このコラム発信は、ユーザーとの接点を増やす戦略として機能しています。サイトには「人気記事ランキング」「特集」「検索機能」が導入されており、興味・関心に応じた記事を探しやすくするナビゲーション設計がなされています。これにより、初回アクセスユーザーを定期読者に育て、信頼感を高めるような導線が構築されています。
さらに、auじぶん銀行はスマホアプリ・UX/UI改善にも注力しています。


アプリとウェブサイトの連携性を強め、操作性を改善することで、ユーザーが情報を得るハードルを下げ、自然にコラムを読む流れを作る設計が評価されています。
また、auじぶん銀行は「お客さま本位の業務運営」の観点から、提供するコンテンツには手数料やリスクの説明を丁寧に行う方針を打ち出しています。コラムだけでなく、商品案内やサポート情報においても、わかりやすさ・透明性を重視し、利用者が安心して内容を受け取れる設計を意識している点が特徴です。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例【SNS編】
銀行業界でも、従来型の広告や店頭プロモーションだけでなく、SNSを活用した「情報発信+顧客接点強化」が注目されています。ここでは、SNS運用で成果を上げている銀行3社の事例を取り上げ、何が成功要因となっているかを整理します。
コンテンツマーケティングの成功事例①三井住友銀行のX


ミドすけだよ!
— 三井住友銀行 公式(ミドすけ) (@smbc_midosuke) October 23, 2025
なんと!#NIKKEI企業キャラクター総選挙2025 で
ボクが初代チャンピオンになったよ★
みんな本当に応援ありがとう!
これからもよろしくね♪
次は日本シリーズ!
ボクも全力で応援する準備中・・・!
一緒に盛り上がろう!#SMBC日本シリーズ2025 pic.twitter.com/3oq94yCLu3
三井住友銀行は、公式のSNSアカウントの中で、特にX(旧Twitter)を積極的に運用しています。フォロワーは30万人を突破しており、公式キャラクター「ミドすけ」を前面に据え、銀行のニュースやサービス情報を硬すぎない語り口で発信することで、親しみやすさとブランド認知を両立しています。たとえば、フォロー&リポストでVポイントやギフトが抽選で当たる投稿など、Xの利用ユーザーが直感的に参加できる内容を発信しています。
ミドすけだよ!#LE_SSERAFIM 初の東京ドーム公演に行けるチャンス!
— 三井住友銀行 公式(ミドすけ) (@smbc_midosuke) September 8, 2025
今なら #Olive の申込・入金で『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』に参加できるキャンペーンをやっているらしいよ!
みんなもチェックしてみてね!
世界的な人気を誇る音楽グループ、LE_SSERAFIMの公演チケットが当たるキャンペーンや、三井住友銀行のバスケットボールチームの試合結果のリポストなど、充実した内容を発信。幅広いユーザーのニーズを満たす投稿を日々投稿している点もポイントです。
また、ミドすけが季節のイベントや行事に合わせてキャラクターの語り口調で投稿するポストも人気を集めています。ユーザーのエンゲージメント向上やフォロワーの離脱防止に向けた日常的な取り組みもSNS運用の成功の要因といえるでしょう。
10月23日は、 #家族写真の日 なんだって!
— 三井住友銀行 公式(ミドすけ) (@smbc_midosuke) October 23, 2025
ボクらも写真館でプロのカメラマンさんに
家族写真を撮ってもらったんだー。
いい記念になるなあ。
ってカエルくんたち、勝手に便乗しないでーっ!!#ミドすけ pic.twitter.com/AxZSy0JqdL
信頼性のある情報発信やフォロワー獲得のための充実した施策、キャラクターコンテンツの発信など幅広い要素で読者のニーズを掴んでいるアカウントは、運用の際に学べる点が多くあります。
コンテンツマーケティングの成功事例②三菱UFJ銀行のInstagram
三菱UFJ銀行は、Instagramを用いて日常生活に密着したお金情報をショート動画(リール)形式で発信する戦略を採用しています。Instagram公式では、貯蓄・節約術、投資、借入・返済など「資産形成に関わる幅広いテーマを、楽しくシンプルに学べるコンテンツ」として提供することを掲げています。
実際の運用例として、電気代節約術や銀行員が実践する日常のお金の使い方、給与振込に関する特典情報(Olive連動など)を織り交ぜた投稿が見られます。これらのリール投稿は再生数1万回を超えるものもあり、認知拡大とフォロワー獲得に成功している点が評価されています。
また、Instagram投稿からストーリーズ等でサービス誘導を行うことで、フォロワーの興味を銀行商品やサービスに段階的に導く動線が設計されています。
コンテンツマーケティングの成功事例③みなと銀行のInstagram
みなと銀行は兵庫県を中心に展開する地域銀行として、InstagramやXを活用した情報発信に力を入れています。特徴的なのは、商品紹介に留まらず「地域密着型の情報」を積極的に発信している点です。
たとえば、兵庫県内のおすすめ観光スポットや季節ごとのイベント情報、地元グルメ紹介など、地域住民が思わず保存したくなる投稿を展開。銀行アカウントでありながらライフスタイルメディアのような役割を果たし、フォロワーの日常に寄り添っています。
さらに教育系コンテンツとして「キッズマネーアカデミー」を実施しているのも特徴です。子ども向けの金銭教育イベントやワークショップを紹介し、親子でお金について学ぶ機会を提供。
こうした投稿は、子育て世帯からの共感を集め、ブランドへの好感度を高めています。加えて、イベント告知や開催レポートをSNSでシェアすることで、オンラインとオフラインをつなぐ接点づくりにも成功。
地域貢献と顧客接点拡大を両立するみなと銀行のSNS運用は、地方銀行の理想的なコンテンツマーケティング事例といえるでしょう。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例【動画メディア編】
銀行が動画メディア(YouTubeなど)を活用して成果を上げる事例も増えてきました。動画は静止画やテキストよりも情報を伝える力が強く、音声・映像・アニメーションを組み合わせることで、複雑な金融知識でも理解しやすくなります。本章では、三菱UFJ銀行を例に、どういった動画設計・運用を行っているかを見ていきましょう。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例①三菱UFJ銀行
三菱UFJ銀行は、公式YouTubeチャンネル「MUFGBankChannel」を通じて、金融情報をわかりやすく伝える動画コンテンツを定期的に発信しています。たとえば、「投資信託とは?資産運用の基本を解説!」といったテーマの動画では、CV(声優)を起用しアニメーション形式で解説されており、金融知識がなくても視聴しやすい工夫が散りばめられています。
また、「NISA制度のポイント」など制度説明動画も提供されており、図解やアニメーションを活用しつつ、声優によるナレーションで情報を伝える形式が見られます。
さらに、三菱UFJ銀行は、動画を通じたアプリ操作説明も行っています。たとえば、「残高証明書はPDFならアプリで即時発行&手数料無料!」という動画では、実際のアプリ画面を見せながら操作手順を解説する形式で、視聴者に利便性を直感的に伝える構成です。
これらの動画は、難しくなりがちなテーマ(相続・NISA・金融制度など)を、視覚的・聴覚的に理解しやすくする役割を果たしています。また、ブランドムービー「エムット始まる」シリーズなど、銀行サービスのコンセプト訴求を兼ねた映像も公開されており、情報提供だけでなくブランド構築の役割を担わせています。
銀行のコンテンツマーケティングの成功事例②七十七銀行
七十七銀行は積極的にコンテンツマーケティングを行っており、再生回数や登録者数を伸ばしています。ここでは、動画活用事例を取り上げ、どのようなテーマや形式で動画コンテンツを展開しているかをご紹介します。
口座関連サービスの一つである「77スマートネクスト」に関する解説動画をYouTube上で公開しており、利用希望者が手続きの流れを視覚的に理解できるよう工夫しています。
動画では、申込み方法や必要書類、注意すべき点などを画面操作とナレーションで丁寧に説明し、初めて利用する顧客でも迷わず手順を追える構成になっています。
銀行でコンテンツマーケティングを成功させるための3つのポイント
銀行におけるコンテンツマーケティングは、商品説明やキャンペーン告知のみにとどまらず、顧客の生活に寄り添い、長期的な信頼関係を築くことが重要です。
金融サービスは一般的に専門的で難しいイメージを持たれがちですが、情報発信の工夫次第で「身近で役立つ存在」としてブランドを確立できます。
ここでは、銀行がコンテンツマーケティングを成功させるために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。


生活者目線のテーマ設定と発信
銀行のコンテンツはお金に関する解説だけでは顧客に響きにくい傾向があります。そのため、日常生活に密着したテーマを取り上げることが効果的です。
例えば、教育費や住宅購入、老後資金といったライフイベントに関連する情報や、キャッシュレス決済やNISAの最新制度など身近な話題を題材にすることで、ユーザーから「自分の暮らしに役立つ情報だ」と感じてもらえます。
さらに、専門用語を避けて図解や動画、インフォグラフィックなどを用いた分かりやすい形式で発信することが重要です。生活者目線のコンテンツは、単なる情報提供にとどまらず、銀行を頼れる相談相手として認識してもらうきっかけになり、信頼関係の強化に直結します。



銀行のコンテンツ発信において生活者目線を持つことは、親しみやすさを演出するだけではなく、顧客にとって実際に役立つ情報を提供することに直結します。教育費や老後資金といった人生の大きなライフイベントだけでなく、日々のキャッシュレス決済や医療費控除、ポイント活用といった小さな工夫も含めて発信することで、幅広い層の共感を得られます。生活の延長線上にあるテーマを扱うことで、銀行は商品を売る存在ではなく暮らしを支えるパートナーとしての位置付けを確立できます。
複数チャネルを組み合わせた戦略
銀行の顧客は年代やライフスタイルによって情報接触の場が異なります。若年層はSNSや動画メディアを好み、中高年層はWeb記事やメールマガジン、シニア層は店舗や紙媒体の方が親和性が高い傾向があります。
そのため、コンテンツは一つのチャネルに依存せず、SNS、YouTube、オウンドメディア、ニュースレターなど複数のチャネルを組み合わせて発信することが成功のカギです。
例えば、YouTubeで投資信託の基礎をアニメーションで解説し、その詳細をオウンドメディア記事で補足、さらにSNSで告知・拡散するといった流れを作れば、幅広い層にリーチしやすくなります。
データ活用と改善サイクルの確立
コンテンツマーケティングを単発の施策で終わらせないためには、効果測定と改善の仕組みを持つことが欠かせません。
記事や動画の閲覧数、SNSでのエンゲージメント率、メルマガの開封率などを分析することで、どのテーマや形式が顧客に響いているかを把握できます。その上で、成果の高いコンテンツは強化し、反応が弱いものは改善や撤退を判断する柔軟さが必要です。
また、データを活用して顧客属性や関心領域を明らかにすることで、今後のコンテンツ設計やターゲティング精度を高めることができます。
コンテンツマーケティングで選ばれる銀行になるために
銀行が競争の激しい金融業界で選ばれるためには、商品や金利の差別化だけでは不十分です。顧客の生活に寄り添い、長期的な関係を築くためのコンテンツマーケティングがますます重要になっています。金融の専門知識を一方的に伝えるのではなく、暮らしに直結するテーマや分かりやすい表現で発信することで、利用者に「この銀行なら信頼できる」と信じてもらうきっかけになります。
また、SNSや動画メディア、オウンドメディアなど複数のチャネルを効果的に組み合わせることで、幅広い世代やニーズに応えることができます。さらにデータ分析をもとに改善を重ねれば、発信の精度が高まり、銀行ブランドの価値を確実に高めることが可能です。
選ばれる銀行となるためのコンテンツ戦略は、一朝一夕で完成するものではありません。計画的にテーマを設定し、発信方法を最適化しながら、顧客にとって価値ある情報を提供し続ける姿勢が求められます。
自社に合った最適な戦略を知りたい方は、ぜひ株式会社ファイマケまでご相談ください。専門知識と実績をもとに、御行の強みを活かしたコンテンツマーケティングをサポートいたします。